とある焼き鳥屋さんにて

すみませーん、カルビとハラミください。
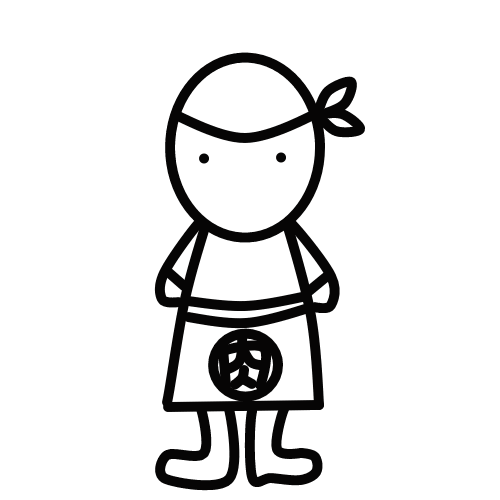
はいよー!塩とタレどっちにしますか?

じゃあどちらとも塩で!
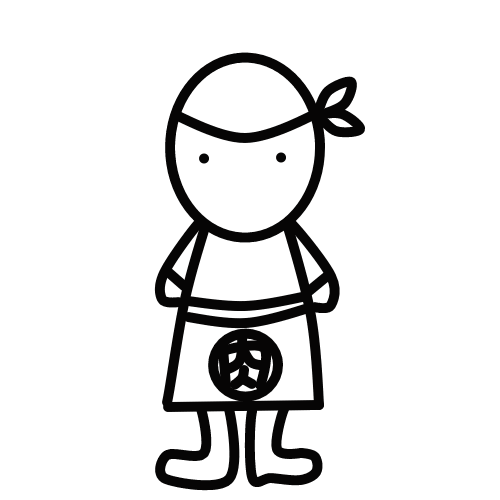
はいよー!
と、よくあるやりとりをして、料理を待つわたし。
しばらくしてやってきたものは
塩味のタレをまとった焼き鳥
焼き鳥の塩とタレの選択で塩を選んだ場合
鶏にぱらりと塩を振ったものを想像しませんか?
塩味のタレは、タレではないのか?
屁理屈っぽいですが、とても疑問に感じました。
タレの定義
ウィキペディアによると
とのこと。概要に
味付けが醤油だけの場合など、調味料が1種類の場合は、一般にタレとは称さない。”
と書いています。
ということは、塩味のタレの正体は一体なんだ!?
塩のタレの内容は
塩で頼んで塩味の液状のものできた場合、ウィキペディアの定義に準ずると
この場合、
塩+水+片栗粉
であれば、塩と言って良いということになります。
調味料が塩のみの場合、片栗粉は調味料には入らないので
塩水にとろみをつけたものは塩で正しいということになります。

塩味にとろみをつけたもののメリット
単純な塩ではなく、あえてとろみをつけることによるメリットとはなんでしょうか。
※以下はわたしの見解です。
作業が単一化される
あらかじめとろみをつけたものを準備しておくことで
オーダーがタレであろうが、塩であろうが
焼く→タレつける
と同じ作業になります。
塩を振る、という作業を覚える必要がないので
作業フロー的には楽になりますね。
味が均等になる
塩を振る、という行為は人によって量がばらつく可能性があります。
液体状にしておけば、かけたりつけたりした後、
余分なところを除けば、味に差が出にくくなります。
また、食べる側もタレが均一にまとわれているのは嬉しいことです。
保存がきく
焼き鳥が串に刺さった状態のものを入荷しているお店もあるかもしれません。
その場合、焼き鳥はあらかじめ工場で作られています。
鮮度を保つために塩分濃度のある液体につけておくことはとても有効です。
つけられた状態で保存されていれば、生肉よりは保存がききますね。
塩味の液体は企業努力の賜物だった

お店で食べる塩味の液体の焼き鳥にも
何かしら努力された結果があるということです。
きっと、
お肉にこだわったり焼いて塩を振ってお客さんに出す、
という技術を養うというのは
想像以上に時間のかかるものだと思います。
これを企業努力でカバーするのはすごいことですね。
一方で、客側も
お店ごとのスタイルを知って自分の好きな店を選ぶという楽しさも生まれます。
こうやって、自分の好きな店を厳選していくんですね。



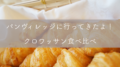

コメント